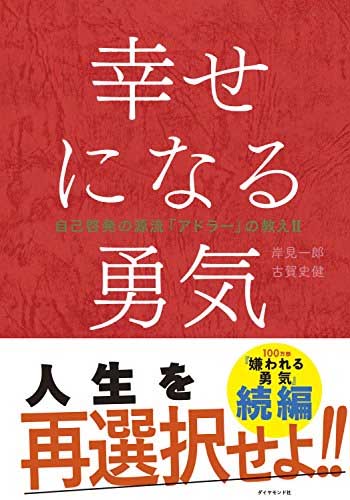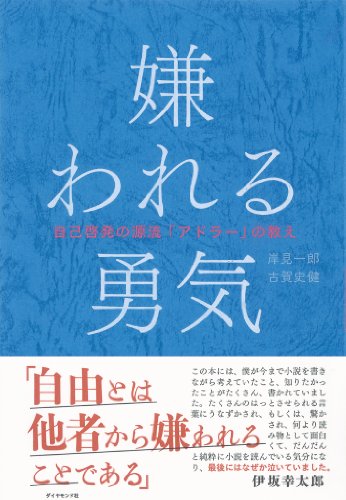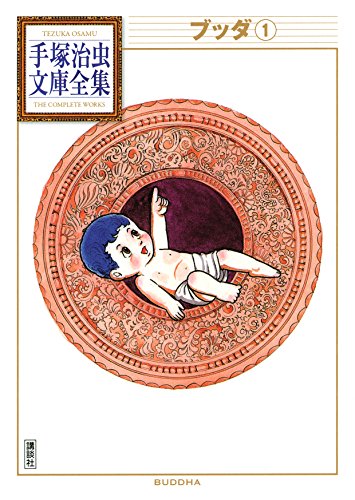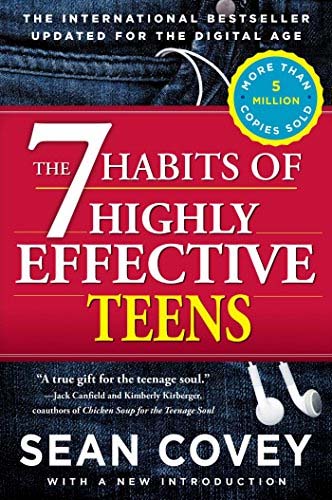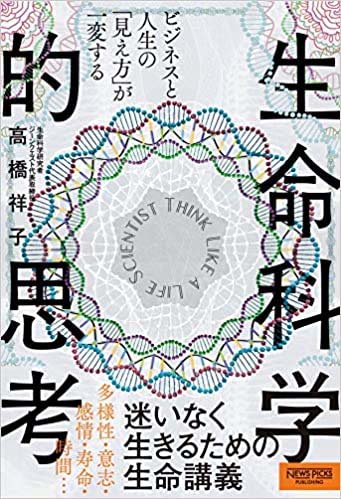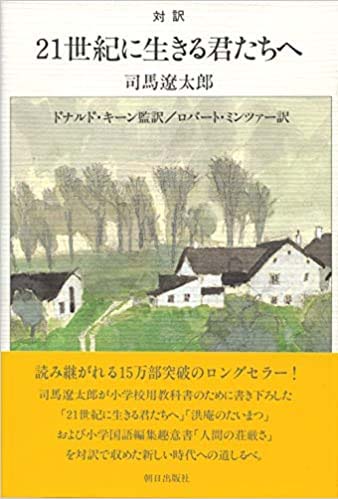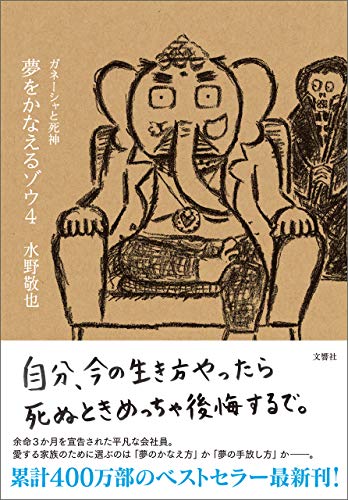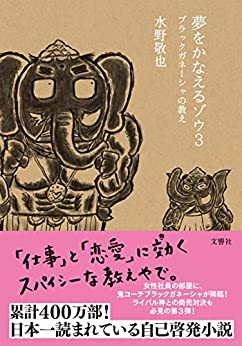2013年に刊行された「嫌われる勇気」の続編、「幸せになる勇気」。
前作と同様、アドラー心理学について、もっと踏み込んだ内容を、青年と哲人の対話形式で綴られています。
「嫌われる勇気」は、自分自身の物事の捉え方について考えさせられる内容でしたが、
「幸せになる勇気」は、特に自分に身近な存在の人達に対して、どのうような心構えで接していくべきか、を特に考えさせられました。
私個人の場合は、子供達と夫が一番に思い浮かびます。
特に、もうすぐ10歳になる長男は、幼少期と異なり、自身で考えて行動することが多くなりました。
それに対して、親側の準備が追いついておらず、予想外の行動に、夫婦で相談する内容が最近増えてきていました。
私がこの本を通じて、特に考えた内容は、大きく3つです。
それぞれ、実生活と照らし合わせて考えてみました。
賞罰の是非
「幸せになる勇気」では、前作でアドラー心理学に感化された「青年」が、図書館員を辞め、中学校教師として働きだした3年後が舞台となっています。
はじめ青年はアドラー心理学に沿った教育法で子供達と接していましたが、
「褒めても叱ってもいけない」
というアドラーの教えに不都合を感じます。
多感な子供達は教師となった青年に反抗し、教室は荒れていました。
青年は、
「規律を守れない子供は叱り、教師は強い態度で接しなければならない。
また、子供のやる気を育て、成功へ導くためには、褒める事は何よりの動機となる。
教育の環境において『賞罰』は必要である。」
という考えに至ります。
青年の話に耳を傾けていた哲人からは、やはり
「褒めても叱ってもいけない」
という言葉が返ってきました。
それはなぜか。
まず哲人は、青年の言動も含め、多くの人達の話の中には
1.悪いあなた
2.可愛そうなわたし
の2つしか存在しないと諭します。
大切なのは、被害者ぶって相手の同情を買おうとすることではなく、常に
3.これからどうするか
という視点で物事を考えなければならないと言います。
これは私にとっても痛い言葉です。
アメリカに来て、自分の思うように仕事が進まなかったとき、人間関係に躓いた時、私の口からは常に被害者意識の塊のような言葉が次々と出てきていました。
このような考え方ではだめだと思いながらも、自分の言動を変える事ができませんでした。
物事がうまくいかない時には、どうしても「自分は悪くない」と思いたくなりがちですが、そんな時ほど、そんな被害者意識の思考回路にストップをかけられるようになりたいです。
そのようにして青年の言動の背景を分析した上で、哲人は、賞罰について話を続けます。
まず、「罰」について。
まず、教室は小さな民主主義国家であり、生徒一人ひとりが国民だと考えること。
先生は独裁者として子供達を支配するのではなく、子供達一人ひとりを、一人の国民として尊重すること。
強い言葉で威嚇したり、罰を与えたりすることは、
先生自身の自立ができておらず、子供達を支配したいという考えの現れである、ということ。
次に、「賞」について。
子供は誰かに認めてもらいたいという気持ちが強く、自分の行動を褒めて貰えればとても喜ぶ。
それが動機になり、もっと頑張ろうとする。
一見良い事のように思えるのですが、哲人はこれを否定します。
つまりは、褒めてもらえば、子供の意識が「褒められること」に向き、それを目的として物事を考えるようになる、という事です。
この考えは、私にとってかなり心当たりがあります。
まずは、叱ることについて。
子供達が何か悪いことをした時、私は、声を荒げてしまうことがあります。
けれども、同じ内容の事が起こっても、声を荒らげないこともあります。
つまり、自分の心に余裕がない時には、手っ取り早く子供達の行動を支配したいために、強い言葉で威嚇してしまうのだと思います。
子供達はそれに気づいているはずです。
次に、褒める事について。
私は、よく子供達を褒めてきました。
褒める事で、子供達の顔がパーっと輝き、
「ねえ見て!こんなんできたんだよ。」
と色々と挑戦した内容を見せに来る子供達を見るのが大好きです。
けれども、時に、3人の子供達を同時に褒めるのは難しいと感じています。
1人を褒めれば、他の1人が嫌な顔をして、
自分のほうができる、と主張してくることがあります。
「これは競争じゃないから。」
と説明してみても、納得することはありません。
子供達にとって、
「いかにして他の兄弟よりも多く褒めてもらえるか。」
が動機になっているような感じがして、とても心配です。
褒めたり叱ったり、子供達の「言動」に対し一つずつ評価をするのではなく、
「生まれてきてくれて、そばにいてくれてありがとう。」
と、相手の「存在」に対して感謝し、信頼を寄せる事が大切なのだと思いました。
ただ、現実的に「まったく褒めない」というのはかなり難しいとも感じます。
もう少し勉強して、自身のアクションプランに落とし込めるようになりたいです。
自立とはなにか
人は、赤ちゃんとして生まれ、子供として過ごす過程において、大人の助けがなければ生きていけません。
そのためには大人に可愛がられる必要があり、子供達はそれを本能でわかっているのだそうです。
どうやって大人の注目を集めるか。
ある時は可愛気があってお利口さんでいることで、
またある時は、困る行動をして、注意を引こうとする。
一見正反対のように見えるこれらの行動は、実は「大人の気を引く」という一つの目的に集約される、とアドラーは説きます。
このように「自分が、自分が」という自己中心的な考えは、子供が生きていくために必要なのだということです。
アドラーによると、この自己中心性から脱却し、
自分が共同体の一部であり、他者に貢献することによって幸せを感じるという、
「共同体感覚(social interest)」
を持って、初めて真に「自立」した人間になるのだそうです。
けれども、大人になってもそのような自己中心的な考えから抜け出せず、自立できない人達がいます。
相手を無条件に信頼すること
では、どうしたら自立した大人になれるのでしょうか。
そこには、前作の「嫌われる勇気(こちら)」でも登場した、
「自己受容」「他者貢献」「他者信頼」
が重要となります。
本書は、心理学の3大巨頭と称される、アルフレッド・アドラーの思想を、アドラー心理学の専門家である岸見一郎氏とライターの古賀史健氏が、青年と哲人の対話という形式でまとめ上げた本です。ざっくり言うと、「他人の目を[…]
ここで詳細は省きますが、特に相手との関係に直接的に影響があるのが、
「他者信頼」
です。
ここで明確にするべきは、「信用」と「信頼」の違い。
「信用」は、銀号がお金を貸す時などに使われるように、その人の背景や行動などの条件によって相手を信じる事。
「信頼」は、相手が誰であれ、無条件に相手を信じる事。
相手から裏切られるかもしれない、相手は自分を搾取しようとしているかもしれない。
けれどもそんなことは、「相手の課題」であって、
「自分の課題」ではありません。
相手に
「裏切らないでね。」
とお願いしたところで、相手がお願い通りに行動するとは限らないのです。
また、そのように相手を疑うことは、相手にも伝わり、自分が相手から信頼されなくなります。
大切なことは、「自分の課題」に目を向け、
相手の行動に関わらず、無条件に相手を信頼し、尊敬すること。
自ら信頼し、尊敬すれば、相手も自分を信頼し、尊敬してくれるようになる。
この「相手を信頼する」という考えは、私にとってまさにタイムリーでした。
長男は、最近マインクラフトというゲームにはまり、そこで仲良くなった友達とチャットをして楽しんでいます。
時間を約束しても、時間内に終わることはなく、「勉強」と偽って自室にこもってゲームやチャットをするようになりました。
私達夫婦は、このようなメリハリのない生活は良くないと考え、何度も長男と話し合いましたが、彼の心に言葉が届いているような気はしません。
PCやアプリにペアレントコントロールを強いて時間内にしかアクセスできないようにしてみたりもしましたが、それで行動に制限はかけられても、彼の考えが変わるようには思えません。
私達は長男の将来を心配しました。
「勉強する」といって部屋に籠もっても、両親の目を逃れてゲームやチャットをしているように思いました。
つまりは、長男を信頼できなくなっていたのです。
哲人によると、相手を自立させるためには、
例えば子供から「遊びに行っていい?」と聞かれたときに、
「いいよ。でも宿題終わってからね。」
と条件をつけるのではなく、
「自分で決めていいんだよ。」
と相手に決断させることが重要、だということです。
子供の行動の決定に条件をつける事は、子供を依存と無責任の地位に置くことだと、哲人は諭します。
長男のPC使用時間やサイトに制限をかけたり、ちょこちょこ様子を覗きに行ったりすることは、彼の自立を妨げる行為に他なりません。
SNSの危険性や効率的な勉強法など、私達の持っている情報を提供し、長男と知識を共有した上で、
その後の行動は彼に決めてもらうべきなのです。
時には誘惑に負けることもあるでしょう。
けれども、私達がまずしなければならないことは、
彼の言動を尊重し、尊敬し、信頼する事なのです。
そこからすべてが始まるのだと、私は思います。
まとめと感想
この本は、他にもパートナーとの関係の築き方等、様々な人間関係構築のあり方について触れられています。
私は、今たまたま子供との関係について強い関心があったので、それを思い描きながら読みました。
結局のところ、私自身がまだまだ「自立」できていないことを実感し、
子供を「自立」に導くような毎日を送るために、自身の「自立」について考える必要があると感じました。
すぐに実践は難しいかもしれませんが、日々考え、行動に移せるようにしたいと思います。
関連書籍